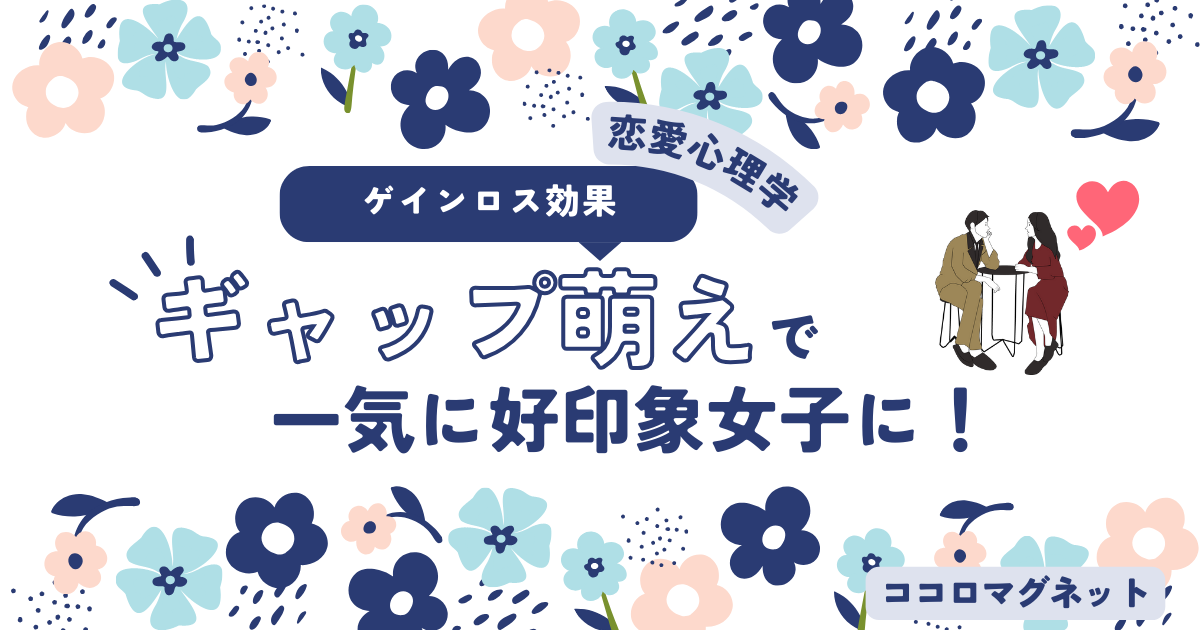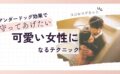「ゲインロス効果」とは、いわゆるギャップのことです。
見た目や普段の印象と異なる言動によって、その人へのイメージがガラリと変わる現象を指します。
些細な言動で、その人に対するイメージが真逆になることがあります。
たとえば、真面目な優等生女子が校則違反のアルバイトをしていると知ったとき、彼女への印象がイメージダウンしてしまいます。
あるいは、不良男子が道端で知らないお年寄りに親切にしているのを見かけたら、彼に対する印象がグッとよくなります。
このように、良くも悪くもギャップによって人からの印象は大きく変化します。
この記事では、この法則を恋愛に活かす方法や実際の体験談を紹介します。
学術的な背景も解説しているので、専門的な知識もつけたい人はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
それでは、ゲインロス効果を使った心理学的テクニックを見ていきましょう!
ゲインロス効果を使った恋愛テクニック

ゲインロス効果において大切なのは、以下のポイントです。
①初対面で頑張りすぎない
②ギャップを意識する
③ネガティブなギャップに注意する
④ナチュラルでいることを忘れない
それぞれ詳しく解説します。
初対面で頑張りすぎない
最初から良い印象を残そうと完璧に振る舞わず、リラックスして会話を楽しみましょう。
最初の印象を継続できなかったときに、「最初はいい人だと思ったけど、実は違うかも」と思われる可能性があるからです。
初対面では少し控えめに振る舞って、次回以降、彼の好みに合わせて印象を変えていきましょう。
ギャップを意識する
ゲインロス効果を恋愛に応用する最大のポイントは「ギャップ」です。
・話し方は落ち着いているのに、思いっきり笑う瞬間がある
・いつも元気で明るいのに、一人で集中して勉強時間を作っている
・クールに見えて、子供に優しい
こうした意外性が「もっと知りたい」と彼の関心を高めます。
ネガティブなギャップに注意する
普段明るくて優しいと思われている人こそ、不機嫌な態度や愚痴っぽい発言には注意しましょう。
「普段は優しいけど、実は愚痴が多い」「最初は丁寧だったけど、だんだん雑になった」などの悪い印象が強く残ってしまいます。
ネガティブな側面を見せるときは、「ちょっと不器用」「緊張しやすい」といった可愛らしい弱点がおすすめです。
ナチュラルでいることを忘れない
演じたキャラや作ったギャップは、長く一緒にいるとどうしても見破られてしまいます。
大切なのは、自分の中に本当にある一面を自然に出すことです。
無理なく見せられる姿だからこそ、彼にとって魅力的に映ります。
体験談〜隣の席の彼はつまんない人?〜

中学生の頃、O君という同級生がいました。
彼はとにかく大人しく、仲の良い一部の男子としか話しているところを見たことがありませんでした。
ある日の席替えで、そんなO君と隣の席になりました。
正直私は最初O君になって残念だと思いました。

話し相手にならないし、1ヶ月退屈しそうだな…
しかし、授業中に先生の小ネタにクスッと笑った彼の横顔を見て、印象が一気に変わったんです。
O君、まさかの笑顔がタレ目系男子だったんです!
ギャップのある可愛い笑顔にやられた私は、どうにかして彼を笑わせたくて積極的に話しかけるようになりました。
恋愛的に発展することはありませんでしたが、どうしてもO君を笑わせるためにあの手この手尽くした私は彼に夢中になっていたのかもしれません。
今思えば、このときまさに普段と違う一面を見て好感度が上がる「ゲインロス効果」が働いていました。
ゲインロス効果の心理学的背景

ここからは、ゲインロス効果について心理学の視点から解説していきます。
- 誰が提唱したの?
- なぜ好感度が急変するの?
- 日常のなかでもよく起きる現象なの?
気になる方はぜひ読んでみてくださいね。
アメリカの心理学者が提唱
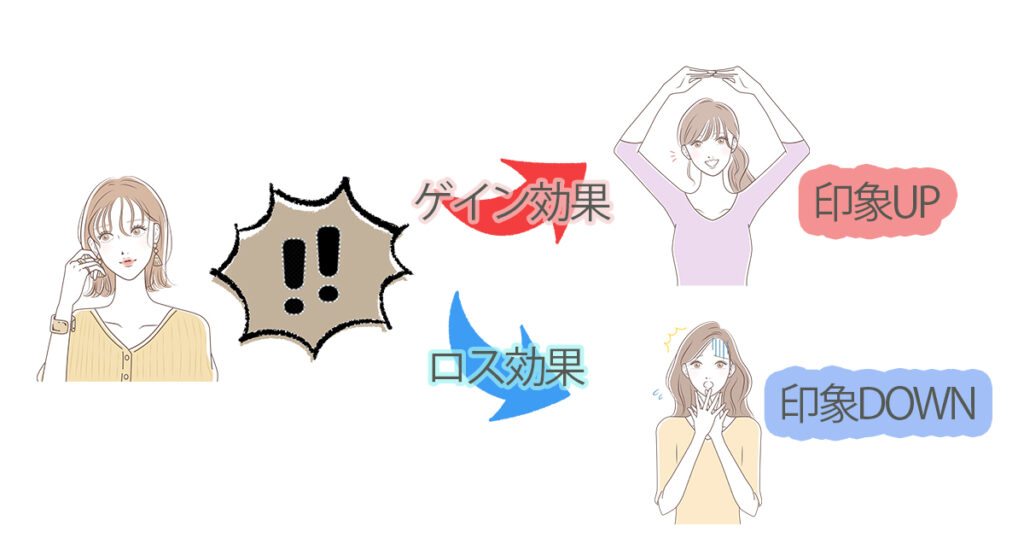
ゲインロス効果は、アメリカの社会心理学者エリオット・アロンソンが提唱したものです。
人の評価が変わるとき、その振れ幅が大きいほど相手への印象が強く残る
という点に、彼は注目しました。
たとえば、最初はそっけなかった相手が徐々に優しくなると「思ったより良い人だ」と感じやすい一方、最初は優しかった人が冷たくなると「裏切られた」と強く感じやすいものです。
アロンソンはこの心理の変化を「ゲイン(上昇)」「ロス(下降)」と名付け、実験を通して効果を確かめました。
アロンソンの実験
1965年、アロンソンは実験を行って、人が「相手をどう好きになるか」に大きな影響を与える要因を明らかにしました。
その実験では、大学の女子学生が「別の学生からの評価」を聞く仕組みが作られていました。
あるときは最初は冷たく評価されていたのに、次第に褒められるようになるパターン。
逆に、最初は高く評価されていたのに、だんだん否定的な評価に変わっていくパターン。
そして、最初から最後までずっとポジティブ、あるいはずっとネガティブというパターンも用意されていました。
結果はとても分かりやすいものでした。
「最初は厳しかったけれど、だんだん認めてくれるようになった相手」が一番好かれ、
逆に「最初は良い印象だったのに後から否定的になった相手」が最も嫌われたのです。
つまり、最終的な評価が同じだったとしても、その途中の“変化の方向”によって人の心は大きく揺さぶられるということが実証されたのです。
脳科学的な仕組み
この現象の背景には、脳が「変化」に敏感だという仕組みがあります。
人は同じ態度や印象が続くよりも、変化が起きたときに強い感情を抱きます。
そのため、最初の印象と違う一面を見せられると「ギャップ」に驚き、強く記憶に残るのです。
ゲインロス効果の具体例
ここからは、学生時代の身近な例「学校の宿題」をお題にします。
まず、ゲイン効果についてです。
これは、普段は宿題を提出しない生徒が、突然宿題を提出した場合に発生します。
宿題を必ず提出している生徒がいつも通り提出しても、それは「当たり前」として評価されません(ゲイン効果は発生しません)。
しかし、普段提出しない生徒が一度宿題を出すと、「あの◯◯さんが宿題を提出した!」と周囲が驚き、好意的に評価されることがあります。
さらに、継続的に宿題を提出するようになれば、「成長した」「変わった」と感じられ、さらに好印象を持たれることになります。
一方で、ロス効果は、最初は宿題を提出していたのに途中から提出しなくなるときに発生します。
元々宿題を提出しなかった生徒よりも「少しはマシ」だと思われることもありますが、それでも「不真面目になった」と評価されることが多いのです。
結果的に、宿題を最初から提出しない生徒よりも悪い印象を与えてしまいます。
最終的に好感度が高いのは誰?

では、最終的に好感度が高いのは誰でしょうか?
「宿題」における好感度ランキングをつけると、以下のようになります。
①途中から宿題を提出するようになった人
②毎回宿題を提出する人
③最初から宿題を提出しない人
④途中から宿題を提出しなくなった人
よいギャップのある女性は魅力的
ゲインロス効果によると、もっとも好感度が高いのは「途中から印象がよくなった人」です。
つまり、第一印象で無理に良い印象を与えようとする必要はないということです。
少しホッとしますよね。
まずは、飾らない自然体の自分で好きな人に接してみて、もし自分が恋愛対象ではないと感じたら、ゲインロス効果を使って逆転を狙ってみるのがおすすめです。
もし好きな人に悪い印象を与えてしまった場合も、ゲインロス効果を思い出して印象がよくなるギャップがないか、探してみてくださいね。
ココロマグネットはいつでもあなたの恋を応援しています。